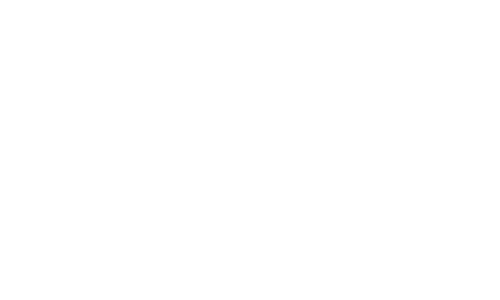UIJターンもローカルも括らない。個別性の価値を伝えていく。

現在、日本は少子高齢化が進み、特に地方においては労働人口の減少に歯止めが効かない状況です。
その反面、テレワークの導入などにより場所を問わず仕事ができるようになったことや、新型コロナウイルスの影響で、地方に移住し就職・転職することが注目されています。
そこで耳にするようになったのが「UIJターン就職・転職」。
しかしながらこの好機を活かしたい仙台・宮城の企業の発信力はまだまだ足りていないように感じます。
当社にもUターンやIターン※1転職・就職で入社した社員がいます。
今回の特集では、その中の社員4名から経験談を話してもらいつつ、当社の強みを活かし「働く場所」としての魅力を発信したい仙台・宮城へどんな働きかけができるのか考えるため、座談会を実施。
また、ファシリテーターには、ローカルに特化した採用・転職支援会社であるリージョンズ株式会社の大石さんをお招きし、幅広い観点から社員の話を引き出し、このテーマについて一緒に考えていただきました。
※1 Uターン…地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住すること。Iターン…地方から都市へ、または都市から地方へ移住すること。(ウィキペディアより)
メンバー

◆Iターン
- メディアクリエイション部 プランニングチーム 曽根 真衣子(左から1番目)
- 地域ブランディング事業部 地域ブランディング1チーム 長谷川 亜実(左から2番目)
◆Uターン
- メディアクリエイション部 デジタルマーケティングチーム 相原 勇士(右から1番目)
- CS事業部 事業開発1チーム 笠原 萌(右から2番目)

◆ファシリテーター
リージョンズ株式会社 執行役員 東北カンパニー長 大石 豊さん
―採用・転職コンサルタントとして宮城・東北に人材を呼ぶことにとどまらず、この地のミライを見つめ様々な活動をされていて、人材や採用に関して、宮城・東北エリアのリアルな現状や課題に見識をお持ちです。
当社も、人材採用全般、JIMOTOコラボインターンシップでご一緒していただいています。
1.どうして「宮城」に?
曽根:ユーメディアではコピーライター、プランナー、machico※2編集部という肩書で幅広く仕事をさせてもらっています。出身は千葉で、前職は東京の広告制作プロダクションで働いていました。
夫が宮城の出身なのですが、東日本大震災をきっかけに「Uターン」したいと言われて。
その時は、結婚前のタイミングだったので、当時は東北に縁もゆかりも興味もなかった私にとっては、結婚するかしないかの選択でもありました。
これは何か縁があるのかなあと思って、自分のサバイバル能力を信じて(笑)移住を決めました。
※2地域コミュニティサイト「せんだいタウン情報machico」。5万人を超える会員(無料)が参加するクチコミ機能やアンケート機能を活用して、プロモーション・市場調査・データ解析などを行っています。
大石さん:そうするともう10年目くらいですか…。
曽根:2013年に引っ越してきて、ジョブレス期間を経て、2014年にユーメディアに入社しました。
大石さん:そうなんですね~。いやあ、すでに聞きたいことはたくさんあるんですけど、まず進めたいと思います(笑)
では長谷川さんお願いします。
長谷川:私は2019年の入社で、営業をしています。出身は熊本で、大学で東京に進学して、そのまま就職して旅行会社と観光局で仕事をしていました。
曽根さんと同じような状況で、福島出身の夫が東日本大震災をきっかけに仙台にJターンしていて、結婚するかしないか、移住するかしないかの選択で、その時はたいそう渋りました(笑)。
宮城が嫌だったというより、20代後半だった当時の私にとっては東京の労働市場は非常に魅力的でしたし、宮城にどんな仕事があるのか、そこでどう評価されるのか、全く想像がつきませんでした。
悩んでいる間に、夫の東京転勤が決まり、“ヤッター”って(笑)。
でも、いずれまた仙台に行くって言うだろうなと思って、地方で働くことを意識して転職しました。
そして2人目の子を妊娠したタイミングで再び移住を切り出されたのですが、予想より早かったので「私のキャリアを返せ~!」とここでもひと悶着ありました。
大石さん:要するにこっちに来たらキャリアが消失すると思ったってことですよね。

長谷川:そうですね、いい仕事が見つかるかただでさえ不安なのに、小さい子供もいたので、最初から“時短でお願いします”って、圧倒的に不利だなと感じていました。
移住して約1年、下の子が1歳になるタイミングで就活を始めたのですが、案の定、面接で“残業できないよね”とか、“ご主人以外でサポートしてくれる方は近くにいますか”とか言われたこともありました。
そんな中、ユーメディアの面接では、子供がいることは全く問題視されず、ユーメディアでも観光関連の仕事が広がってきたところだったので、入社することになりました。
大石さん:曽根さんと長谷川さんは完全に東北に対してマイナスからのスタート(笑)ですね。でもニコニコ話してくださるので、後でまた詳しく聞きたいです。
では、今度はUターンのお二人ですね。笠原さんお願いします。
笠原:私は2019年に新卒で入社しました。営業職で、一般企業と学校などが主なお客さんです。出身は宮城県で、大学進学のため茨城県に移りました。
芸術系の学部だったので、初めはデザイナーや制作職志望で東京で就職活動をしていましたが、なかなかうまくいきませんでした。
理由を考えたとき、東京で暮らすイメージができないからだと思ったんです。自分の中でストレスに感じる要因が多くて。私は働くことだけではなく生活する環境も大事にしたいのだと気が付きました。
さらに震災も経験していたことで、地元を離れてからいろいろ感じたことがあって…家族もいる地元の宮城で暮らしたいと思ったことがUターンした経緯です。

相原:僕は2020年入社で、出身は宮城の角田市です。2013年に山形の大学に進学して、大学4年の頃に友人とWeb系の会社を起業し、約2年経った時に事業拡大のため、東京移転を決めました。
東京に出ることを周りに相談した時は、“なぜ山形や宮城で事業を続けないの?”や“地元に貢献する形の事業をしないの?”など、お叱りやアドバイスをいただいたことを覚えていますが、もちろん事業の観点から、首都圏に移転する明確な理由もありました。
そうして東京で働いている中で、2019年の台風19号で地元が大きな被害を受けました。
実家も大きな被害に遭い、家族が精神的にも経済的にもきつく、自分が地元に戻って来る必要がある状況になったことが、Uターンを考えたひとつのきっかけです。
起業した会社ではWebサービスやスマホ向けアプリなど様々な事業をしており、学んだことも多かったため、宮城でも魅力的で面白い事業をやっている企業を探していたところ、ユーメディアに出逢いました。
大石さん:なるほど~。これは一人一人それぞれに一時間くらいかけて話を聞きたいですね(笑)
2.ユーメディアを通してみた「宮城・仙台」での仕事と生活
大石さん:それぞれドラマがありますし、一緒くたに語れないし、UIJターンって言葉は便利でよく使われますけど、やっぱりそれで括れないですよね。
うちのブランドスローガンに“暮らしたいところで思い切り働く“っていうのがあるんですけど、こういうバックグラウンドで実際に「宮城・仙台」に来られて、長谷川さんはどうですか?
長谷川:一番不安を持っていたところがクリアになったので、今は快適に暮らしています。
地方こそ能動的に楽しんでいかないといけないだろうなとは想像していたのですが、今の仕事でも、生活でも、それがおもしろさであり、難しさだなと思っています。
大石さん:生活するのに何か自発的な働きかけがないといけないものだと思っていたし今も思っているっていうことですよね。
曽根さんはどうですか。

曽根:私は考えるより先に行動するタイプなので(笑) 勢いで仙台に移住したら、コピーライターの求人が一つもない(汗)って驚きました。
そんな中ユーメディアのグループ会社であるプレスアートの編集部に応募して、ユーメディアを紹介してもらって入社したんです。
東京ではスキル特化型で、主に言葉を追求するコピーライターとしての仕事しかしていなかったんですが、仙台はコンパクトな分まちづくりに関わる大型案件にダイレクトに携われるのが、おもしろいですね。
machicoもコミュニティサイトという枠に捉われず、そのリソースを使って街を元気にしていく仕組みや仕掛けを考えていくというミッションがあるので、おもしろいです。
長谷川:自分の仕事がみえるのが面白い時もあれば、その責任の重さが怖くなることもありますよね。
相原:僕は、地方はお客様の理解を求められる水準が高い気がしていて。
東京のWeb業界では、最先端はこうで世の中のトレンドはどうとか、定量的で事業やサービスが成功するための根拠や情報が揃っていれば、ステークホルダーに伝わるんですけど、こっちでそれは通用しないことが多くて。
大石さん:すごくわかりますね。首都圏では一般化、抽象化されたものが通用するんですけど、ローカルは個別性がより高い感じがするんですよね。
相原:そうですね。レベルが高い低いといった比較や差ではなくて、文化が違えば言語も違うし、物事の伝え方が違ってくる、ということだと思います。
だから、その違いを理解するためにも、地域の観光資源やイベントなどの情報にアンテナを張って、「地元住民であらねばならない」みたいな感覚はありますね。

笠原:営業していて思うのは、お客さんが地元民に優しいことが多いということですかね(笑)
そういうつながりへの意識が強かったり、身近に感じてもらったりしやすいのかな。そういった意味では営業として働きやすいなって思います。
長谷川:逆に大石さんに質問なんですが、首都圏の方から東北の人とは仕事がしにくいと言われませんか?私は全然そうは感じていなくて、そういう考え方や固定観念が邪魔だなと思うことがあります。
大石さん:僕も長谷川さんのおっしゃる通りだと思っています。でも確かに、一部ありますね。
相原さんが言ったような観点で、言語が違うとみられる時もあるし、こっちが逆にそうみるときもあるし。中に入れない感みたいなところもあります。
でも、首都圏とローカルで何か違うのか、そもそも、そう考えているうちは進まないなと。その辺で、みなさんが地域をどう捉えてどう発信していくかは重要なテーマだと思う。
相原:『誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成における実証事業』という事業で白石川堤一目千本桜のライトアップ映像をYouTube広告で世界に向けて配信した経験から学んだことですが、今や自分で撮った写真・動画をインターネットで気軽に発信できる時代です。
その中で、ユーメディアとして地域コンテンツを映像や写真、文章にしていく価値は何か?を考えたとき、首都圏とローカルの違いみたいな考え方ではなく、地域の個別性をどんな切り口で、どんなストーリーを混ぜ込んでカタチにしていくか、を考えることが大切だと思いました。
また、地域の良さを発信するときに、地元→宮城→日本→世界の順に知ってもらうのが一般的かもしれないんですけど、地元→世界にひとっ飛びしちゃう発想で、世界目線や全国目線でコンテンツ創りができた事例になりました。
地域でも、そういう考え方や働き方ができるんだということが伝われば、もっとUターンする人も増えるのかなって思います。
関連記事
【2021年04月特集】白石川堤一目千本桜を通して見えた東北とユーメディアグループの姿
3.ローカルでは括れない個別性と可能性

大石さん:僕のユーメディアさんに対する期待でもあるんですけど、相原さんの話や今日の全体の話を聞いてもそうなんだけど、仙台は仙台だし熊本は熊本だし、ローカルで括れないですよね。
仙台だって俺は俺だし笠原さんは笠原さんだし、そこの個別性がきちっと伝わっていくといいなと思うんです。
これが見えないから東京にいたときの長谷川さんのような状況が起きるんですよ。仙台・東北で大きく括られて、“何もないでしょ”みたいな。そうじゃなくて。
東京で、仙台にこういうことをやっている会社があるって話をすると、“へえ~!おもしろいですね~”ってなるんですよ。この個別性が重要なんです。
これを発掘して表に出していくべきなんですけど、これを各社でやろうとしても大変なんですよ。埋没したままになるケースが多いから、それをユーメディアさんにはキュレーションしてほしいんです。
均社長の話を聞いてもそうなんですけど、例えばRoute227s‘Cafeや仙台オクトーバーフェストのように、物理的にキュレーションする、引っ張って来て発信することができるのがユーメディアさんだと思うんです。
価値は個別性なので、実は東京で暮らすことの固有性とこっちで暮らすことの固有性には接点があるよみたいなことだと思っているんです。
それがつなげたらいいなって。それをつなげるのが僕の中ではユーメディアさんで。
それを引っ張ってきて、さあどうぞ、ってやれる会社ってそんなにないなと。
曽根:せんだいタウン情報machicoには『東北はたらきスタ!』というインタビューコーナーがあります。そのコーナーでは東北で働くいろいろな方のライフスタイルを紹介していきたいと思っています。

大石さん:それはいいですね!ぜひどんどんお願いします。
事例をもう一つ言うと、本社を東京から東北の某市に移したアパレルメーカーがあって、なんでかって言うと、例えばイタリアに商売にいったときに、東京から来ましたって言うよりも、ジャパンのトウホクから来ましたっていう方が、響くそうなんです。
そういう時代なんですよね。こういう土地の固有性が重要だと思うんです。
ローカリズムとグローバリズムはこんな感じで関係を結ぶような気がするんです。これはコロナの後押しでより強固なものになると思います。
地方→東京→グローバルはよくて、地方からグローバルはダメなの?っていうことですよね。
そこにはまだ言葉やメンタリティの断絶があるので、それを飛び越えないといけないんですけど、そこはユーメディアに考えてほしいなって期待しています(笑)
曽根:観光プロモーションに関わって感じるのが、ひとつの自治体の魅力を一言で表すのはなかなか難しいということです。
ターゲットとなる人たちの興味関心も多岐に渡ってきているので、それぞれ刺さるものが違いますし。地域にあるさまざまな小粒の魅力を、“地域”という括りではまとめられないのかなという気がしています。
“仙台”ではなくそこにある価値をフィーチャーしたほうが、可能性は広がるのかな…。
大石さん:すごくわかるなあ。だけど結果的に仙台固有の価値とその小粒の価値ってリンクしていると思います。
曽根:確かにそうですね。地域のエッセンスは、何物にも代えがたい価値ではありますよね。
大石さん:それが“らしさ”で。それがフラットに並んでいる状態になるんだろうな。ましてやテレワークも普及してこれから東京の会社の仕事をこっちでやるみたいなことが増えるかもしれないですよね。
そうした中で“らしさ”がフラット化していけたらいいな。だからこそ個性は何?ってなるとは思うんですけど。
長谷川:ユーメディアに入ったからなのか、仙台に来たからなのかはわかりませんが、個性は意識するようになりましたね。
今は働く選択肢も増えて、“地方でどうやってお金稼ごう”という時代からは変わったなと感じています。
大石さん:そうした時に逆に、じゃあ何で仙台に暮らしているんだっけ?ってなると思うんです。
でも、だけど仙台がいいんだよなって、言語化できないけど感じているものが理屈抜きであるんですよね。僕もUターンした人間ですけどその時にS-styleとか見ましたもん。
いろいろ事情はありますけど、Uターンする人ってそうなんですよ。Iターンはこれとはまた違うと思うんですけど。だからUIJターンで括れないんです。
長谷川:曽根さんと私の場合、UやJについてきたIってことですもんね(笑)
例えば、夫に何かがあっても、私が熊本や東京に戻るかっていうと戻らなくて、たぶん仙台に残ってそのまま仕事するかなって、夫と話しています。
大石さん:べたなところで言うと、転勤してきた人が定着しやすいとこがあるんですよ。細かい理由はあるんですけど、ハード面ではない質感に言葉を与えることが大事だと思います。
一般化されないものの集合体としてローカルはあると思うので、それをユーメディアのみなさんがカタチにしてもらえるといいなって思います。
編集後記
特集のテーマであった「UIJターン」ですが、一度の座談会では到底語り切れない深いテーマであることがわかりました。
仙台・宮城を「ローカル」で括らず、その中に存在する確かな個別性。当社はそれを発掘しつなげる、キュレーションする、はたまたそんな場をつくる。
しかしそこで、単体ではなく地元企業や官学と連携し、エリアの魅力を高めるつながりを生み出していく。
仙台・宮城という地域の可能性と広がり、そこで果たすべき当社の役割を考えさせられる座談会となりました。
Credit
Writer/阿部ちはる