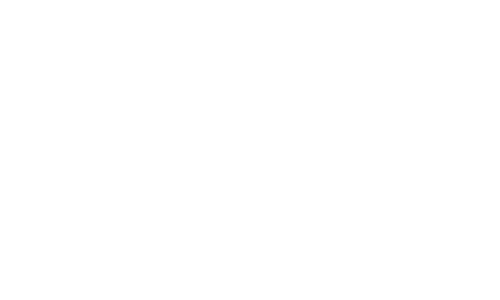学生と地域の化学反応で宮城をもっとおもしろく。未来につながる“産学○○”?(後編)
地域の未来を担う若者と、いかにお互いが楽しみながら宮城のこれからを共創できるか。このことを「ちいきのミライ、わたしたちから」をグループクレドとする当社は、事業活動や大学との授業連携等を通じて追及しています。本記事では、今年度の学生との取り組みを事例に、冒頭の問いを読者の皆さんとともに考えていきます。
本記事は、前後編の記事となります。
前編では、今年度実施した東北工業大学様との授業連携にフォーカスし、大学教員の視点で、産学連携が生み出すシナジーへの期待や、地域と学生の未来に軸足を置いた産学連携のこれからについてお伺いしています。
後編では、当社の社員による視点で、当社が学生との取り組みを行う意義や、取り組みをより価値として広げていくには何ができるかを、座談会を通して考えていきます。
前編こちらから
目次
1.地域×デザイン case:東北工業大学 産業デザイン学科との授業連携
2.工場と団地と地域のリノベーション case:東北工業大学 建築学科との授業連携
1.既存の枠組みに当てはめない「学びの場の創出」
2.学生と地域が主体となるまちづくり「未来型の地域連携」
3.学生の可能性を信じて問いを立てる「ブレークスルー思考」
取材対象者
モデレーター:CS・地域ブランディング事業部 執行役員 佐々木 和之
座談会メンバー:CS事業部 笠原 萌、大沼 紗采
地域ブランディング事業部 武田 国大、佐藤 碧伊
メディアクリエイション部 澤田 朱里、森 健

既存の枠組みに当てはめない「学びの場の創出」
佐々木 仙台市・宮城県の学生が就職を機に県外に流出している現状に対し、地域企業が学生に知られていないことに加え、まだまだ地域企業の魅力が足りないのではないかと考えます。産学連携というと、一緒にものづくりをすることが多いけど、当社は、前述のことから、これまで様々な形で大学とコラボをしてきました。この座談会を経て、産学連携という言葉自体が違う意味を持ったものになってくれたら嬉しいなと思っています。
笠原 東北工業大学様の「地域×デザイン」の授業で講評をさせていただき、地域の魅力を知ってもらう機会をもっと私たちもつくっていきたいと感じました。今回、授業の課題を通して学生は地域を深堀りしましたが、課題以外のところでも宮城県の各地域に足を運び知るきっかけをいっぱいつくれたらなと。

講評会の様子
大沼 今回の工大の授業は、地域を外側から俯瞰してみるのではなく、自分が地域に入っていって当事者になって考えるプロセスがありました。こうやって当事者になる意識の醸成は重要だなと思います。講評の場で、学生は今回それを実感できた授業だったんだなと感じましたね。
笠原 自分の観点をしっかりもっていましたね。企業側の目線で感想を伝えることが、学生にとっては学びになるんだなと思いました。私たちが普段仕事でアウトプットしていることが、学生にとっては「仕事としてやるっていうのはこういうことなんだ・・!」と新鮮に感じたと思います。だから意外と肩肘張らずともいい協働ができるんですよね。先生の熱意や学生のスタンスが揃っていることで、お互いそんなに構えなくても得られるものが大きいのかもしれないですね。
佐々木 授業に社員を派遣するだけじゃなく、企業がこういう場を提供していきたいよね。学生が自然に入ってこられるような。先生と私たちというより、複数の大学が入れるコラボの場をつくっていけたら。そういう場にもなったらいいなと思っているのが、旧工場のリノベーションです。それを東北工業大学の建築学科の学生の授業の題材にしてくれました。
佐藤 今回はクライアント・工場・団地の未来のことを頭に入れつつ、将来性のある提案が求められる授業でした。授業が始まる時には、前段として、新工場の機能説明や、旧工場を実際に見てもらい、昔はどのように使っていたかを説明しました。あとは、質疑応答形式で学生さんから意見を募りつつ回答する感じで、当社の現在の事業領域や展望、工場視点でどうやりたいか、営業視点ではどう使っていきたいかを説明しました。
佐々木 中間発表と成果発表は、印刷に関してはネガティブな意見が多かったですね。印刷はこの先あんまり…みたいな。この忖度ないのが、学生の良さだと思います。当社は、それを冷静に受け止めながら、改めて印刷の価値やその先の成長を考えられました。
佐藤 学生さんも団地に足を踏み入れることってないですし、今はそもそもそういう場所ではないので、開かれた団地・工場というアウトプットが学生の好奇心にもつながったかなと思います。

佐々木 齋藤さんとの話の中(前編)で、仙台で頑張れば世界に進出できると思っているという言葉に、私たちもやっていることに自信をもって、それを伝えていくことも大事なんだなと勇気をもらったよね。地域企業がどんどん大きく成長していくことによって、学生にも魅力に感じてもらえるんだと。こういう気持ちを一緒にもってくれる企業や大学と一緒にチャレンジしていきたいですね。そのための拠点を今検討していますので、楽しみにしていてほしいなと思います。
学生と地域が主体となるまちづくり「未来型の地域連携」
佐々木 TAUラウンドテーブルは、授業ではなく、大学と企業と地域が一緒にまちづくりに取り組む活動で2年目になりますが、改めて簡単に活動の経緯や活動概要について教えてください。
武田 東北学院大学の五橋キャンパスが開学し、私たちも学生も通うエリアをひとつの「地域」として捉えて、若者がムーブメントを起こせる街にしていきたいと、キャンパスがある五橋と当社が拠点を置く土樋、その間にある荒町商店街の方に入っていただき、3者でラウンドテーブルをスタートさせました。ちょうどCOLORweb※のリブランディングも考えている時期だったので、COLORwebも絡ませながら、学生主体の活動を何かできないかとさらに再考しました。
※COLORweb…仙台・宮城の学生が主体となって運営するWebメディアであり、当社のメディアブランドのひとつです。ブログでの情報発信をメインに、当社が関わる事業にも参画し、学生ならではの視点で、調査や取材を行っています。
関連記事:学生と新しいローカルをつくる ーCOLORwebが築くメディアの価値とそのミライー
佐々木 ラウンドテーブルの場づくりはどうしているの?
武田 最初は試行錯誤の連続でした…。もともと、東北学院大学さんは当社のお客様でもあり、どうしても私たちも「提案」というスタイルが染みついてしまっていて、なかなか理想のラウンドテーブルの形になれていませんでした。そこで、当社からまずは変わる必要があると思い、ある時から「提案」をやめて、あえてあまり準備をせず、集まった場で出てきた意見に対してみんなでブラッシュアップするという形になり、1年かけて現在はラウンドテーブルの姿に近づいていると感じます。
 TAUラウンドテーブルの打合せ中の1枚。東北学院大学五橋キャンパスの「未来の扉センター」で。学生と荒町商店街の方、当社メンバー。
TAUラウンドテーブルの打合せ中の1枚。東北学院大学五橋キャンパスの「未来の扉センター」で。学生と荒町商店街の方、当社メンバー。
今年度からは大きく2つのプロジェクトを月1の定例のミーティングをやりながら進行しています。1つは、荒町の良さを若者に伝え、未来に残すための「マップづくり」、もう1つは荒町に新たな常識をつくることを目指し、後世に伝えていけるような、みんなで踊れる「荒町の踊り」をつくろうというプロジェクトです。
佐々木 誰かが回すとかではなく、平場感がいいんだね。学生は何人くらい参加しているの?
澤田 学生はコアメンバーが8人くらいで、2年生と4年生が半数ずつという感じです。
佐々木 ユーメディアはその学生の活動を傍らで見ている感じ?
武田 私たちも一緒に入ってやっています。もちろん商店街の方も大学の方も入ってもらっています。
佐々木 これは特に単位になるわけではないの?
武田 これは完全に課外で、任意参加ですね。
森 参加してくれている子の中には「専攻で地域づくりを学んでいてそこに役立つと思った」「授業では座学で終わってしまうけど、このプロジェクトではそれを自分でやってみることができる」といったことをモチベーションにして参加している学生がいます。
「産学連携」も、こちらからの押し付けでは全然進まないんだということをこのプロジェクトで改めて学びました。「産学“連携”」だけではなくて、一緒に何か見出していく「産学“共創”」さらには、共に思わず前のめりに参加してしまうという意味で「産学“共犯”」関係をつくっていくやり方が必要だと思います。そのために、このプロジェクトでも学生への問いかけ方を工夫しました。例えば、地域でデザインをやってみようという時に一般的には「何をつくる?」から考え始めると思うんですが、「この地域に流れる変えた方がいい常識ってないかな?」と探してもらって、「それ、ぶっ壊そうよ」と。「何を壊すか?」を考えてもらったらそれが突破口になって面白いアイディアが出てきたり、学生自身が自分事としてプロジェクトに参加してくれるようになりました。“問い”をどうつくっていくか、が関係性をつくっていく上で大切だなと思いました。
澤田 学生もはじめは「何をしたらいいんだろう?」という感じでしたよね。しかし今は、学生のやりたいことを引き出して、そこにこのプロジェクトのねらいをうまく乗せていくことができるようになったのかなと思います。この流れを続けていきながら、当社や商店街と一緒に取り組めるからこそできるプロジェクト・アクションにしていけたらいいなと思います。うまくサポートできると当社の価値にもつながっていくと思います。
佐々木 学生から「これやりたい!」ってスムーズに出てくるもの?
澤田 いきなり最初から出してもらうのは難しいですよね。COLORwebのメンバーもそうですが、森さんがさっき言ってくれたような導きや問いがあって初めて「これに興味がある」「これをやりたい」という思いが生まれてきます。
佐々木 場だけつくってもダメなのかもね。
学生の可能性を信じて問いを立てる「ブレークスルー思考」
佐々木 仙台市の「若者目線によるまちづくり情報の発信事業」をCOLORwebとやってくれています。COLORwebは長く澤田さんが担ってくれて来たけど、今の課題とか、考えていることなどを聞かせてください。
澤田 現在のCOLORwebの学生メンバーは10人くらいで、週1回ミーティングをしながら自分たちで記事の企画を考え、取材~記事の投稿まで全てを担ってくれています。長く学生のみなさんと一緒に活動してきて思うのは、私たちから地域にまつわるさまざまな気づきや問い・魅力を伝えて、いかに学生の気持ちをモチベートできるかどうかがうまく連携していくための鍵だと思っています。学生のみなさんが自ら興味を持ったことにチャレンジできる環境を一緒につくることは当然ですが、「実は他にもこんなにおもしろいことがこの地域にはあるんだよ」と新しい世界に導いてあげることも大切。そうすることで初めて、学生の力と地域の可能性が両方広がっていくと思うんです。COLORwebのリブランディングも、地域にある課題をみんなで考える、まちづくりに自分たちが積極的に関わっていく要素を入れることを軸としています。そういった点に仙台市様が共感してくださってこの事業につながったことは、本当に貴重な機会になりました。
森 仙台市としても若者がまちづくりに参加するための活動や取り組みをたくさん提供されているのですが、その情報が広く若者に届いていないのではないかという課題をもたれています。仙台市からの情報となると行政からの発信だと思われ、自分事化されにくいのではといった仮説もあったので、自分の友達やクラスメイトからの発信のようになればもっと興味をもってくれるのではないかと思いました。「まちづくり」というキーワードがハードルを高く見せるのでは?という学生の意見をもとに、敢えてそのキーワードを使わずに、「仙台で0⇄1(ゼロからイチを生み出すこと)を楽しんでいる人たちってこんな人がいます」という発信の仕方をしようと、「SENDAI0⇄1PROJECT」というプロジェクト名にしました。仙台にもっとこんなコトがあったらいいのに…を「じゃあ自分でつくっちゃおう!」と行動を起こしている人を紹介していきたいと思っています。フランクに学生がコミュニケーションできる姿が理想です。
佐々木 私たちから学生に向けて、楽しさを知ってもらうとか、自分たちで生み出していこうよと転換してあげないと、宮城に残って一緒に取り組んでくれる若者はいなくなってしまいますよね。行政や大学や企業の目線・狙いはだいだい揃っているけど、その中に学生の視点がまだないのかもしれない。当社は、学生と関わる中でいろんなことを学生の方から教わっていますし、学生の気付きにハッとさせられることも多いです。学生の可能性や力を信じて一緒に活動できていることは当社の強みだと思います。
短期的なマネタイズを前提とするとできることが小さくなってしまうので、まずは自社のメディアやリソース・拠点を使った仕組みづくりや学生を巻き込む経験をしながら、それを活かして新たな価値を生み出すことができると信じています。
編集後記
前編と後編に分けて、それぞれの視点で産学連携を紐解くと、学生と地域を一番前に置いて考える、学生と真摯に向き合う、様々な共創の姿がありました。”産学○○”?の答えが今すぐ出るものではありませんが、私たちはそれを問い続けながら、既存の枠にとらわれず変化していきます。
私たちが学生の歩む道を引くのではなく、学生自身がゆたかな未来を描けるように可能性を広げる。そこに地域でコトを起こすおもしろさや地域でチャレンジできる働きがいを見つけてもらえたら嬉しい。地域企業として地域とともに魅力を発信し、問う力を磨いていきます。
credit
Writer/阿部 ちはる